令和6年度の税理士試験の消費税法に合格し、簿記論・財務諸表論・消費税法の3科目を揃えました。
しかし、これ以上試験を続けても膨大な時間がかかり、合格の見通しが立たないため、大学院免除を目指すことにしました。
もちろん時間をかければ必ず合格する試験であることは間違いないのですが、あと2科目(そのうち所得税or法人税が残っている)の試験は最低でも私の能力では4〜5年はかかることと、大学院に進めば上手くいけば2年で免除申請できることを天秤にかけた結果、大学院を受験することにしました。地方なので通える範囲に大学院がないため、通信制の大学院に絞った結果、東亜大学大学院を受験することに決めました。田舎に暮らす社会人でも通信制なら頑張れそうだと感じました。また、試験は小論文のみで、面接や研究計画書も不要だったため、ここしかないと考え受験しました。
結果無事合格することができました。例年3倍前後(近年はもっと高いのかな?今年は4倍近くあったのかも)の合格率であり、過去問の練習も制限時間内に書き終わったこともなく、これといった対策も十分にできないまま受験を迎えたため、合格発表までビクビクしていましたが、なんとか合格出来て良かったです。
12月頃に試験対策として過去問を請求したり、まいこさんのnoteの記事を購入して読んだり、小論文対策の本を購入したりしたのですが、どれも受験対策としてしっくりこず、本格的に意識して取り組み始めたのは2月に入ってからでした。結局最後までどうやって小論文を書いたら合格点まで到達できるのかはわからず、何故合格できたのかもよくわかりませんが……。
以下に東亜大学大学院を受験してみて思ったことを書いてみます。
一般的な大学院受験対策は必要ない?
東亜大学大学院の入試科目は小論文のみですが、大学院入学後に論文を書く素質がある人物かどうかを選定する試験であるはずです。また、法律の専門的な知識も必要とされないことは公式HPにも書かれており、理論的な考察力と表現力を見るのが目的とのことです。
過去問を見てわかる通り、例年通りですと(2024年分除く)民法に関する判例が2つ与えられ、それぞれについて要約と自分の意見を論理的に述べる問題です。
私は小論文の試験は1回も受けたことがなかったため、一応複数の書籍を購入したり、まいこさんの東亜大学通信制大学院受験攻略note記事を購入したりして対策しようとしました。書籍に関してはブログやXでおすすめされていた一般的な大学院入試に関する対策本を読みましたが、過去問と、本に載っている対策とが上手く噛み合わず、具体的対策としてはあまり意味がないような気がしました(原稿用紙の使い方などの形式的な小論文作成のルールは勉強になりましたが)。書籍によって紹介されている小論文の「型」などの書き方が違うし、結局どの方法が東亜大学大学院受験向けなのか訳がわからなくなってしまいました。
まいこさんのnoteに関しては、具体的な小論文作成手順や「構成メモ」、「問題文を書き写す」などの攻略法は自分にとっては不向きな対策であったものの、東亜大学通信制大学院受験に特化しているので、特に解答例などは非常に参考になりました。その他の入試情報もかなり有益だと思います。
Xなどを見ていると予備校や添削サービスでしっかり対策していた人が不合格になっている知らせを数多く見ました。合格発表当日は、Xでしっかりお金をかけて受験対策していた人が「不合格だった」という投稿を2つほど見たので、「私なんて絶対受かってないじゃん」と思ってその日は合格発表のページを見なかったくらいです。次の日に一応確認してみたら自分の受験番号があって非常に驚きました。
思うに、東亜大学大学院法学専攻の試験は判例を読んで要約したり、法律に関する修士論文を作成するための論理的な文章を書く力を見ているため、一般的な受験対策は功を奏しにくいのでは。
ただ単に、法的三段論法を意識しながら、事実関係に着目し、結論に繋げる。基本はこのやり方でOKで、過去問3年分を時間を測って解いてみて、まいこさんの解答例を参考にする。今思うと、この対策方法が私にとっては有効な手段でした。文章の雰囲気や構成・考え方(思考回路)、言葉の選び方を東亜大学大学院受験向けにセットするために、後述する「判例百選シリーズ」もかなり役立ちました。
要約の問題はどうやって対策すればいいのか試験直前までわかりませんでしたが、そもそも問題文の判決の抜粋が要約ですし、三段論法的な構成になっているので、正直な話、そのまま字数制限に沿うような形でコンパクトに書き写すしかないという結論に至りました。意外と簡単です。抜粋を読みながら、結論である決定的な文章と事実関係に蛍光マーカーで線を引きながら、たまに自分なりの言葉で簡単に箇条書きでメモしたり、矢印を書いて反対する意見を書いて、それらを基に要約文を書きます。「どのような理由付けによって」その結論になったかを書かなければならない場合は、最後の段落で「このような(上記のような)理由付けによってこうなった。」と書くことを意識しました。
自分の意見を述べる問題は、どちらの判決を支持するかという問題が近年の傾向だと思いますが、こちらに関しても、根拠を厚く書ける方を選んで問題文の中からキーワードを拾って結論に繋げるように書きます。根拠の箇所に、自分が考えた具体的な例示を挟むと好印象なのでは、と思います。私が受けた年の問題は公園を自分の住所と言い張るホームレスの判例でしたが、想定される反論に対するアンサーも一応書いた気がします。「常識的に考えてこうだろ」と思うことについて、「社会通念上の〇〇に照らして〇〇は合理的である」、「他の法体系やその他法令などを総合的に勘案すると〇〇の方が合理的である」みたいなそれっぽい言葉のチョイスも大事かもしれません。あと「法(の)解釈」というキーワードもどこかに入れると東亜大学大学院向けの小論文になるような気がします。
試験日が近づくにつれて、ネットで調べたら出てきた「弥生カレッジCMC」の受験対策講座や「論文オンライン」の添削サービスを受ければ良かった、などと後悔していましたが、ふたを開けてみればその必要がなかったことがわかりました。2月に入ってからの勉強(対策)でも、間に合いますし、添削サービスや講座受講しなくても、小論文素人でも合格できるということです(少なくとも今年度の試験までは)。
買った書籍など
大学院・大学編入学 社会人入試の小論文 改訂版 思考のメソッドとまとめ方
東亜大学大学院法学専攻の受験に成功した人のブログでこちらを買ったという記事を見たため(その人も効果があったかわからないと書いていましたが)、8月の試験が終わった後すぐに購入しました。8月に買いましたがちゃんと読み始めたのは年明けくらいです。内容的には結構難しいです。一般の大学院向けにはいいとは思いますが、問われていることが少し特殊な東亜大学院の試験にはあまり役立たないかな、という印象です。巻末に主な大学院の過去問が抜粋されていますが、東亜大学大学院法学専攻の過去問も載っています(解答例はないです)。
序章と、一応要約の仕方の章もあるのでそこだけ読みました。要約の方法については「作者が言いたいことを抜き出してそれを軸に文章をまとめる」みたいな方法が掲載されていたと思いますが、やはりこの点も東亜大学大学院向けではないと思います。
ただ、2024年度の試験においては判例の問題ではなく、書籍からの引用でしたので、そのような場合にはこちらの本が役に立つのかもしれません。
当日の受験会場でも試験開始までの時間にこの本を読んでいる人を見かけました。
全試験対応! 直前でも一発合格! 落とされない小論文【増補改訂版】
こちらも、東亜大学大学院に合格した人がXで紹介していたので、8月の試験が終わった後すぐに購入しましたが、ちゃんと読み始めたのは12月くらいからです。ところどころページをめくったくらいですが、「大学院・大学編入学 社会人入試の小論文 改訂版 思考のメソッドとまとめ方」よりも内容はわかりやすいし、こちらの方がどちらかというと東亜大学大学院向けだと思います。ですので、この本は買って読んだ方がいいかもしれません。全部は読まなくていいと思います。軽く流し読む程度で。
小論文の超基本のルール(原稿用紙へのマスの使い方など)は小論文初心者にとってはありがたかったですし、間違いやすい漢字も載っていたのでその点は現在手書きで文字を書く機会が減っており漢字が全然書けない私にとっては良かったです。半分以上のページは読んでいませんが、一応試験前日に頻出テーマの速習表の章でジャンル的に距離が近そうな部分をピックアップして軽く読みました(教養として知っておいた方がいい社会問題について一応見ておくか、という程度です)。
まいこさんのnote「東亜大学通信制大学院受験攻略」
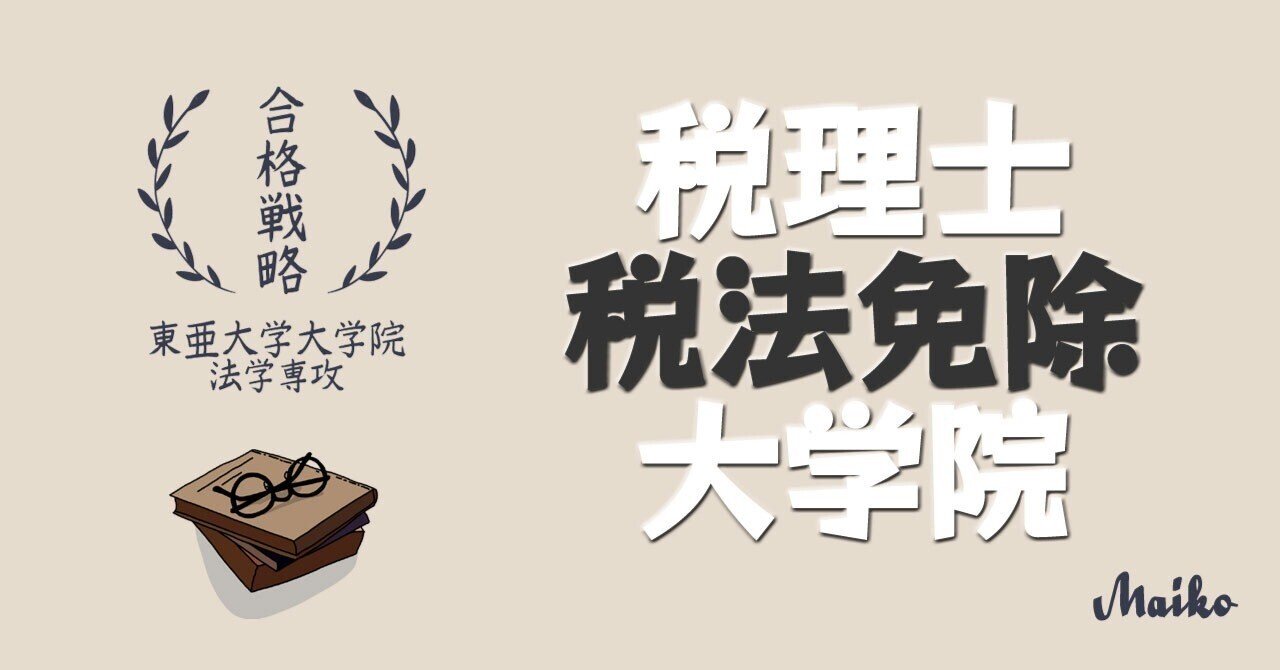
このnoteに関しては東亜大学大学院法学専攻を受験する人は大多数の人が見たことあるのでは?と推測します。東亜大学大学院で勉強している(していた)まいこさんという方が受験攻略方法を一部有料の記事で公開しています。私だけかもしれませんが、webで東亜大学大学院と検索すると公式HPでなく、このnoteがトップに表示されます。そして大学院の公式ページは何故かヒットしずらいです。
具体的な解答への道筋についての解説だけでなく、問題を作っていると思われる先生とその先生の専門分野についてや、そこから導かれる次回以降の問題の予想など、非常に有益な情報が書いてあります。練習用の原稿用紙もPDFで置いてありますので非常に助かりました。購入する価値はあると思います。私は購入して印刷して読んでました。
ただ、具体的な攻略法を読んでも自分にとってはつかみどころがないというか、あまり理解できませんでした。私がアホでノロいだけなのですが、「構成メモ」の書き方も使い方もよくわかりませんでしたし、「問題文を書き写す」というやり方も私にとってはそのまま写すのは時間の無駄と思ってしまいました。字を書くのが遅い私は過去問の練習で時間内に終わった試しがなく、本試験で初めてギリギリセーフで書き終えることができました。noteの記事には急におすすめの文房具を紹介するパートが出てきたりして少し混乱しましたが、消しゴムはおすすめされていたものを購入しました。欲を言えばシャーペンも紹介してほしかったです笑。シャーペンを使う機会が滅多にないため久しぶりにシャーペンを3つほど購入してみたのですが、どれも使い勝手が悪く、試験当日も苦労しました。
解答例と練習用の原稿用紙が非常にありがたかったです。私は2022年度、2023年度、2024年度の記事を購入しました。多くの人がこのnoteを見ていると思います。
論文オンライン(小論文書き方バイブル)

私は受けていませんが、東亜大学大学院対策の小論文の添削を受けられるサービスがあるそうです。この添削サービスを利用して対策している人も多いそうですが、しっかり対策しても不合格になったという声も見ましたし、繰り返しの添削のおかげで合格したという意見も見ました。今はまいこさんが解答例を出してくれているので良いですが、今後、模範解答がないため自分の答案が合格レベルなのか確かめたい場合は利用するのもいいかもしれません。
また、メルマガ登録すると、「小論文書き方バイブル」という40ページの冊子が無料でダウンロードできます。メールアドレスは捨てメールアドでOKです(ドロップボックスのダウンロードリンクとパスワードがアドレスに送れられてきます)。
「小論文書き方バイブル」も小論文の作成の基本的なことが書いてありますが、気になるところだけ読めばいいと思います。プロット作成の方法も数種類紹介されています。
少し前は課金しなくても予想問題と過去3年よりも前の過去問をダウンロードできたのですが、今は出来なくなっています。違うサイトだったのかな?
法と社会: 新しい法学入門 (中公新書 125)
2024年の試験では、それまでとは出典元が変わり、書籍からの引用になりました。詳しくはまいこさんのnoteを参照してください。試験問題で出題された書籍は古いものであるため、書店では買えません。この本は東亜大学大学院の講義でも扱うそうなので、もし次回も同著もしくは同著者の書籍から引用されて出題された場合に備えて、著者である碧海純一さんの本を軽く読んでおこう、ということで購入しました。Amazonで普通に買えます。2月に入ってから買って、半分くらいしか読んでません(全部読もうと思い試験に向かう電車の中でも読みましたが間に合いませんでした)。著者の論じている専門分野の考え方が同じ著者の問題が出たとき参考になるかもと思ったのですが結局元通りの出題形式に変わったので意味はありませんでした。読み物としてはまずまずの本だと思うので買って後悔はしていません。
判例百選(別冊ジュリスト)
これを買って読んだことが最も有意義な試験対策だったかもしれません。購入したのは、「租税判例百選」「民法判例百選Ⅰ」、「会社法判例百選」「商標・意匠・不正競争判例百選」の4冊です。「租税判例百選」は試験が終わったばかりの8月に電子版で購入しましたが、東亜大学大学院の試験では租税法は出題されないということが過去問を調べるうちに判明し、慌てて2月に入ってから「民法」、「会社法」、「商標・意匠・不正競争」を購入しました。租税法に関する論文を書くために入学するのに、税法に関する判例は出ないんかい、とツッコミをいれたくなります。近年の試験は民法から出題されておりますが、それ以前は会社法から出題されていたようです。また、まいこさんのnoteを読み、一応最後に「商標・意匠・不正競争」を購入して少し読んでみましたが、有名な芸能人の裁判例などが載っていてとっつきやすかったです。
今思えば買うのは民法だけでよかったですがその時は「別の分野から出題されるかも」と不安で気付いたら合計4冊も購入してしまいました。会社法なんて多分4ページくらいしか読んでない。
このシリーズはそれぞれのトピックごとの有名な事件について、事件の概要と判旨、解説が記載されており、法律を勉強したことのない人からすると、読み物としては割とヘヴィーな本です。理解するのに時間がかかる事件と解説も多いですが、受験対策として、法学の論文特有の文章の書き方や言い回しや用語に慣れることができますし、自分でもそのような言葉を使えるようになります。この点は結構重要なことなのでは、と思います。また要約の練習をすることも可能で、「判旨」が要約文の参考にもなります。解説文も自分の意見を述べる練習をする際にも有効です。私は「判例百選」を使って文章を書く練習はやりませんでしたが、頭の中で構成を考えたり、「こういう文章で書き始めよう」とか、読みながら意識づけしていました。
私は受験当日の試験会場までの荷物を極力減らしたかったのでどれを持って行こうか迷いましたが、「大学院・大学編入学 社会人入試の小論文 改訂版 思考のメソッドとまとめ方」以外は持っていき、試験開始の時間までちらほらと目を通していました。
「大した対策はしていない」と書きましたが、こうしてみるとちょっとはやってますね。笑
でも本は本当にちょっとずつしか読んでいません。
受験当日の様子など
東京は70〜80人くらいはいたのかな?もしかするともっといたかもしれません。集合時間が9時半で、試験開始が10時から(試験のアナウンスは10分前くらいから)だったので、その間にコンビニでパンを買って食べました。集合時間で9時40分でいいのでは、とどうでもいいことを思いました。
試験官には「教えてみき先生! 税法論文ってどう書くの?」をはじめとする本を出版されている脇田弥輝先生もいました。
会場では「大学院・大学編入学 社会人入試の小論文 改訂版 思考のメソッドとまとめ方」を読んでいる人を見かけましたが、過去問を見ている人が多かった印象です。税理士試験の勉強で大原やTACに行ってた時に見かけた人が会場にいて、「やっぱり皆んな東亜大学大学院を狙ってるんだなぁ」と思い、受かる自信がなくなったことも覚えています。
問題用紙が配られた際にくれぐれも「問題をネットで販売したりしないように」との注意がありました。過去の販売していた人がいたそうです。「この問題の著作権は東亜大学大学院にあります。特にあなた方は法律を学ぶために入学しようとしているのだから、そういった行為はくれぐれもしないように」とのことでした。そりゃそうだ。試験室(東京会場)には時計もありました。蛍光マーカーは使用OKです。定規も試験官に確認を受ければ使用可能でした(私は使用しませんでしたが)。
あと、税理士試験では絶対ありえないことですが、問題の内容が注意事項が書かれた表紙の上から透けて見えてました。
試験が2023年までと同じ2つの判例の形式の問題に戻っていましたが、予想外だったのは、2つとも同じ事件を扱った判決の抜粋でした。だからこそ書きやすかったとも言えますが。違う事件だったら時間が足りてなかったかも。あと原稿用紙もマスが指定文字より多くは書けないようになっていました。
時間ギリギリまで書いてなんとか最低文字数はクリアできたかな、という手応えでした。誤字や脱字をチェックする時間がなく、過去問を解いた時も誤字脱字をしなかったことがなかったため、そこが心配でしたがなんとか合格できてよかったです。入学後のこれからが本当の頑張りどころです。
最後に
東亜大学大学院法学専攻の受験は、一般的な小論文対策とは少し異なる特殊性があります。私の経験を通して感じたのは、法的な文章の書き方や判例の読み方に慣れることが何よりも重要だということです。
判例百選シリーズを読むことで法律文書特有の表現や論理構成に触れることができましたし、過去問を実際に時間を測って解くことで試験の感覚をつかむことができました。予備校や添削サービスに頼らなくても、自分で判例を読み込み、論理的な文章を書く練習を重ねれば十分合格できる試験だと思います。
税理士試験のように膨大な知識を詰め込む必要はなく、短期間の対策でも合格可能です。私のように2月から本格的に対策を始めても間に合いますし、法律の専門知識がなくても論理的思考力と表現力があれば十分です。
これから受験される方がこの体験記を読んで少しでも参考になれば幸いです。ただし、以上の対策はただの私の感想として現時点で言えることであり、次年度以後の試験がどうなるかわかりませんので、あくまで参考程度にしていただければ。
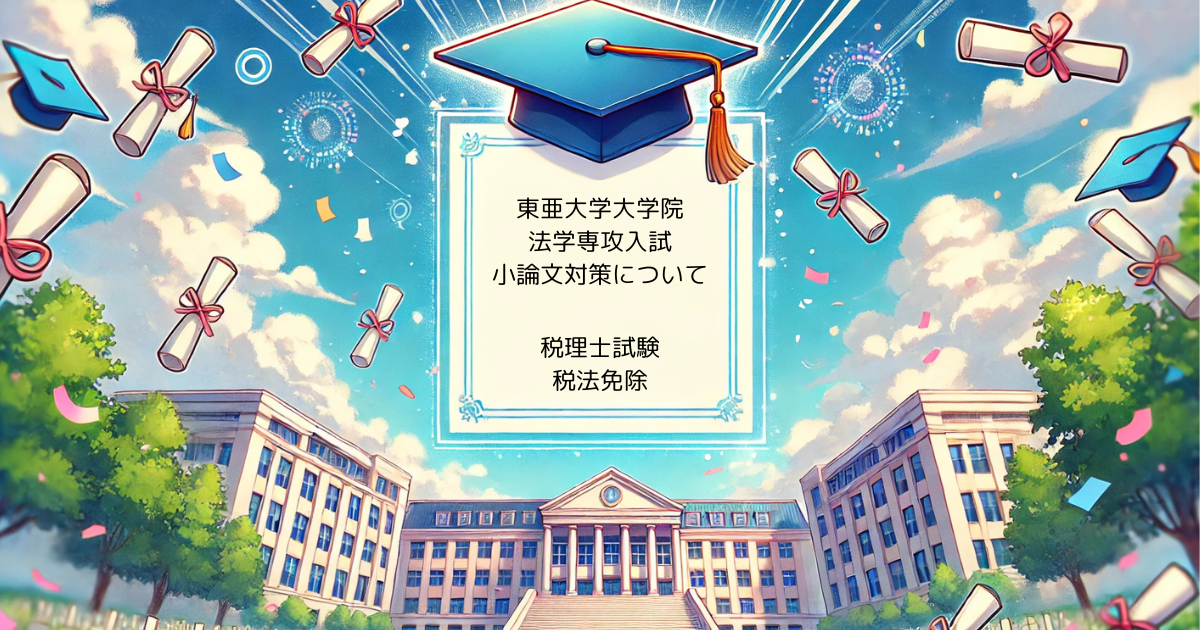








コメント